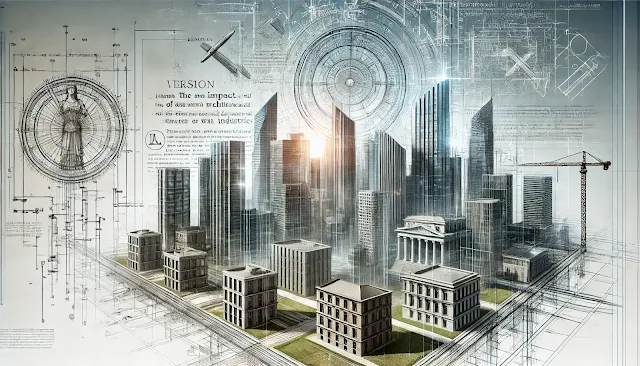住宅の新築やリフォームを考える中で、
「地震に強い家にしたいけど、確認申請まではしたくない」
というご相談をいただくことがあります。
実は、確認申請をしなくても、耐震等級3相当の性能を目指すことは可能なんです。
今回は、一級建築士としての視点と、現場経験をふまえて
「確認申請なしで耐震等級3を実現する方法」について、わかりやすく解説します。
確認申請とは?出さなくても良いケースがある?
確認申請とは、建築物の安全性や法規制を第三者に審査してもらう制度です。
ですが、以下のような条件を満たせば、申請が不要なケースもあります:
-
木造住宅で2階建て以下
-
延べ床面積が100㎡以下(約30坪)
-
防火地域・準防火地域外
-
増改築で軽微な構造変更のみ
こうしたケースでは、確認申請を省略して建築することができます。
耐震等級3とは?どれくらい強いの?
耐震等級は、住宅性能表示制度の中で定められており、以下のように分類されます:
-
等級1:建築基準法レベル(震度6強~7に一度耐えられる)
-
等級2:等級1の1.25倍の耐震性(学校などの基準)
-
等級3:等級1の1.5倍の耐震性(消防署・警察署などと同等)
つまり、等級3は最も強いレベルの耐震性を持つ住宅とされています。
確認申請なしでも「等級3相当」はつくれる?
結論から言うと、認定は取れなくても、設計・施工次第で耐震等級3と同等の構造性能を実現することは可能です。
そのポイントは、次のような設計・施工の工夫にあります。
✅ 壁量を十分に確保する
耐震性の基本は「壁の強さと量」。
建築基準法で定められた壁量の1.5倍程度を目安に設計することで、等級3相当を目指せます。
✅ 壁の配置バランスを取る(偏心率の調整)
強い壁が片側に寄っていると、地震時に建物が“ねじれ”てしまう原因になります。
バランスよく耐力壁を配置することで、構造全体の安定性が向上します。
✅ 接合部を金物でしっかり補強する
柱や梁、筋交いのつなぎ目を、構造金物で確実に補強することも重要です。
ここが弱いと、いくら壁が強くても壊れてしまいます。
✅ 床構面を固める(剛床構造)
地震の力は横方向にも伝わります。
そのため、床や屋根の面を構造用合板などで強化し、全体で地震力を分散させることが求められます。
申請しない場合の注意点
確認申請を出さないからといって、自由気ままに建てていいというわけではありません。
以下のような注意点があります:
-
耐震設計に詳しい建築士や施工者との連携が不可欠
-
自己判断ではなく、簡易的な構造チェックは必須
-
フラット35や性能表示制度を使う場合は、申請が必要になる
安心を担保しながらコストを抑えたい場合は、「耐震等級3相当」の設計ができる専門家に相談するのがベストです。
実際の相談事例
-
「リフォームで申請不要の規模だけど、耐震強化したい」
-
「100㎡未満の新築を考えていて、コストは抑えたい」
-
「耐震等級の“証明”はいらないけど、安全性は確保したい」
このようなニーズに対し、確認申請を行わず、耐震等級3に相当する構造を目指すサポートを行っています。
まとめ:確認申請なしでも、安心できる家はつくれる
-
耐震等級3は「認定」だけが目的ではない
-
構造の工夫と施工の精度で「等級3相当」は実現可能
-
費用や手間を抑えつつ、安心感を持てる家づくりができる
「確認申請が面倒だから」と最低限の性能にしてしまうのではなく、
正しい知識と信頼できる設計・施工で、コストと安心のバランスをとった家づくりが可能です。
ご相談はこちらからどうぞ
ご自身のケースで「どこまで耐震性を確保できるか」「申請は本当に必要か」など、
不安な点がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。